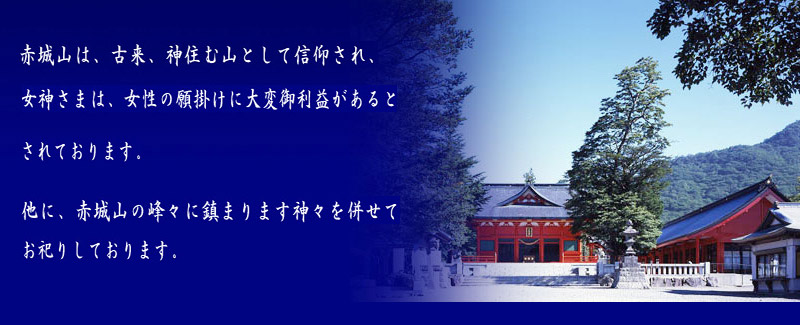 |
|
| 主な御祈願 | |
| 心身健康 ・ 無病息災 ・ 病気平癒 ・ 開運招福 ・ 家内安全 ・ 商売繁盛 ・ 社運隆昌交通安全 ・ 旅行安全 ・ 工事安全 学業成就 ・ 試験合格 ・ 芸事上達 ・ 必勝 ・ 当選 ・ 良縁 ・ 縁結び ・ 子授け ・ 安産 ・ 子育て ・ 初宮詣 ・ 七五三 厄除け ・ 方位除け ・ 心願成就 ・ 他 |
|
| 御祈願のご案内 | |
| 清らかな赤城山、永い歴史と伝統の赤城神社で、皆様が「赤城大明神」さまの御神徳によって、より一層発展されますよう御祈願を奉仕しております。 |
|
| 受付場所 |  受付場所 |
|
神社本殿に向かいまして、右側の授与所受付で、お申し込みください。 電話・ファクシミリでの予約も承ります。 ※御祈願申込書はこちらよりプリントできます。 |
|
| 御祈願殿 |  御祈願殿  御祈願殿 内部 |
|
受付が終わりましたら、待合室でお待ち下さい。 係の者が、御祈願殿にご案内します。 御祈願殿は、平成18年、大同元年(806年)に赤城神社が、大洞の地に御遷座されてから、1200年を記念し斎行された大祭に建設されました。平成17年神社本殿、拝殿の修復がなされ、その間、御神座がお納めされておりました。現在、皆様の御祈願が、ここで御奉仕されております。 |
|
| 受付時間 |  |
| 午前9:30〜午後4:30まで(4月1日より11月30日) 午前10:00〜午後4:00まで(12月1日より3月31日) 日によって、祭典等の都合により、御祈願をお受け出来ない時間がございますので、ご確認ください。 |
|
| 初穂料・玉串料(御祈願料) | |
|
1件につき、5000円より承っております。 初穂料によりまして、御神札・記念品が異なります。 |
|
| 神棚のご都合により、特に小さな御札を希望される方は、お申し込みの際、お知らせください。 10名以上の団体(会社・各種法人・組合等)の御祈願は、20000円より承ります。 社運・企業隆昌・商売繁盛・工事安全祈願・交通安全祈願・他 |
|
| 御予約 | |
|
電話またはファクシミリでの、御予約を受け付けております。 お待ちいただくこと無く、御祈願が受けられます。 御予約の後、確認の連絡をさせていただきます。 御予約後の日時の変更も可能です。 ※御祈願申込書はこちらよりプリントできます。 |
|
| ◇人生のお祭り◇ | |
 |
|
| 子授け祈願 | |
| 古代の信仰では、山に女神さまが住み、たくさんの神様を産み共に暮らし、人々を守ってくれていると信じられていました。古来、人々は山に行き、子授けや安産を願っていたのです。 | |
| 着帯と安産祈願 | |
| 子供を授かったことを、神様に感謝し妊娠五カ月の戌の日に、岩田帯をしめます。犬のように安産で、岩のように丈夫に育ちますようにという意味です。無事に健康な赤ちゃんが、生まれますようにと安産祈願が行われます。 特に、戌の日に限らずに、体調と良い日を選ばれてもよろしいでしょう。 |
|
| 命名 | |
| 赤ちゃんが誕生。人の一生は「名付け」に始まります。一生名乗る名前ですから、素晴らしい名前を付けてあげたいものです。印象・響きも良く、そして幸運を招く名前であったら、人生において、何よりも強い勇気と自信になることでしょう。古くから、言葉に魂がこもり、その「言魂」・「ことだま」によって、人間性が生かされると信じられてきたのです。名前は、無形の財産であり、後の世まで、その人を伝える貴重なものです。 ・ ご両親・ご家族の希望にそった、開運命名を行っております。 ・ 命名には、時間をいただいております。余裕をもってお申込みください。 ・ お申込みの状況によって、お受けできないこともあります。 |
|
| 初宮詣とお食い初め | |
| 赤ちゃんが、無事に誕生したことに感謝し、これからも健やかに成長出来ますように御祈願します。一般的に、男の子は生後31日、女の子は生後33日目に行います。これは、あくまで目安とし、赤ちゃんの体調や天候等を考慮して、お出かけください。 また、生後100日目頃に、赤ちゃんに食事を食べさせます。箸初め・百日祝とも呼ばれています。赤ちゃんが、一生、食べるものに困らず、幸せであるようにと願う儀式です。小さな赤ちゃんですから、食べ物は、食べさせずに、口に付けるだけで大丈夫です。初宮詣祈願に記念品として、お食い初めの器をお渡ししております。 |
|
| 七五三参り | |
| 11月15日。一般的に、3歳の女の子。5歳の男の子。7歳の女の子。のお祝いで、成長を神様に感謝し、これからの無事と健康を祈願します。 3歳は髪置、5歳は袴着、7歳は帯解と言われ、古くからの習慣によるものです。近年は、11月15日に限らず、その前後の良い日行われております。 御祈願は、随時、受け付けております。 |
|
| 十三参り | |
| 女子が、数え13歳になると、帯をつける盛装をしてお参りをします。 正式な成人式を迎える前の重要な年と考えられ、また、かつての女子の成人式であったとされております。 |
|
| 入学・卒業のお祝い | |
| 入学・卒業など生活環境が変わる時も、大きな節目です。 |
|
| 学業成就祈願・試験合格祈願 | |
| 学校教育は大切なことです。日頃の学習が身につき、実力を十分に発揮し、目指す学校や職場の試験に、見事合格できますように、神様に御祈願いたします。 |
|
| 成人のお祝い | |
| 20歳になり、無事に大人の仲間入りができたことに感謝し、お祝いします。昔の武家の「元服式」公家の「初冠の儀」で、厳粛な大人への節目の儀式だったのです。自己の責任だけでなく、社会への義務と他人への思いやりの備わった人と成るべく神様にお誓いします。 |
|
| 厄祓い・方位除け |  方位除け年齢(令和3年)  |
| 厄年は、災難や障りが身に降りかかりやすい年のことです。神様の御加護をいただき、災難が身におよばぬように、厄祓いの御祈願を行います。 男性の厄年は 25歳・42歳・61歳 女性の厄年は 19歳・33歳・37歳・61歳 その前後を前厄・後厄と言います。特に、男性の42歳、女性の33歳は大厄とされています。(一般的に数え年で行われます。) 方位には、年周りによって避けなければならない方角があります。また、方角は、その年によって変わります。 ※ 右の方位除け年齢(令和3年)は、PDFファイルで開きます。 |
|
| 交通安全祈願・自動車のお祓い | |
| 社会に出ると、自動車の運転は必要不可欠なものとなるでしょう。安全運転に心掛けるとともに、神様の御加護をいただき、無事故でありますように御祈願いたします。 |
|
| 結婚のお祝い |  結婚式 |
| 結婚は大きな節目です。御縁によって結ばれた二人が、新しい人生の門出を祝い、幾久しく幸せな家庭を築くことを誓います。 御神前での結婚式は、お二人だけ、また御家族・親族での落ち着いた式や、お友達や多くの仲間とともにお祝いすることも出来ます。最大80名まで御参列できます。フォーマル・カジュアル、衣装はお好みで、厳粛な気持ちで御参列ください。 |
|
| 良縁祈願 |  良縁祈願 |
| 妹背の契りを結ぶ伴侶。 良い御縁に巡り合えますようにと御祈願がなされます。 |
|
| 結婚記念日のお祝い | |
| いろんなことがある結婚生活。二人ともども健康で過ごせたことに、感謝し、これからも二人、力を合わせ良い家庭を築くことを誓います。 一般的な結婚記念日 紙婚式(満1年)、木婚式(満5年)、錫婚式(満10年)、水晶婚式(満15年)、陶器婚式(満20年)、銀婚式(満25年)、 金婚式(満50年)、金剛石婚式(満75年) |
|
| 家内安全・開運招福祈願 | |
| 結婚式や、思い出の日に、家内安全・開運招福の御祈願をされ、末永く幸福で、子孫が繁栄されるように、神様にお願いされてはいかがですか。 |
|
| 長寿のお祝い | |
| 延命長寿に感謝いたします。 還暦(61歳)十干・十二支の組み合わせは60通りあり、自分の生まれ年の干支が廻って来るのは61年後となります。生まれ直すという意味で、赤い頭巾やチャンチャンコが送られます。 古希(70歳)「人生七十、古来稀なり」との言葉からつけられました。 喜寿(77歳)喜という文字が、七・十・七に分けられることからつけられました。その他に、 傘寿(80歳)、半寿(81歳)、米寿(88歳)、卒寿(90歳) 白寿(99歳)、上寿(100歳)、茶寿(108歳)、皇寿(111歳)などがあります。長寿であることは、大変おめでたいことです。一家そろってお祝いをします。 |
|
| 五節句 | |
年中行事の中の、重要な日のことをいいます。 1月7日 人日(じんじつ)の節句、七草の入った粥を食べ、無病息災を祈ります。 3月3日 上巳(じょうし)の節句・ひな祭り 3月最初の巳の日を節句として祭っていましたが、後に3月3日に行うようになりました。 自分の厄を人形に託して、厄を海や川に流しお祓いをする風習でした。 これが、ひな祭りに変わり、女子の幸せを願うお祭りになったのです。 5月5日 端午(たんご)節句 五月は物忌みの月とされ、5月5日に菖蒲の葉を風呂に入れ浴する習わしがありました。 菖蒲は薬草で、邪気を祓い心を清め、火災を防ぐとも信じられておりました。 菖蒲の音が、尚武に通じ男の子の節句となりました。 立身出世するように、鯉のぼりが揚げられ、強さを意味する武者人形が、飾られるようになったのです。 7月7日 夏の夜空を飾る天の川、織女と牽牛が年に一度7月7日の夜に出会う、中国の星まつりに由来するお祭り。 奈良時代には、広く行われていました。 笹につけた飾りを流し、いろんな災いをお祓いしたものです。 読み書き、技芸の上達を祈願するお祭りでもあります。 9月9日 重陽の節句 陽は生を意味する。 陽(奇数)の最大数である、九が重なることから不老長寿の祈願日とされる。 菊を酒に浮かべ、飲むとこから菊の節句ともいう。 |
|